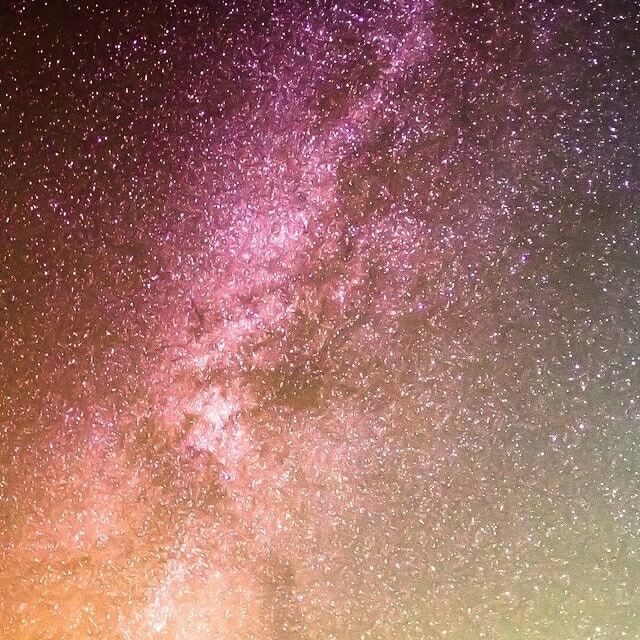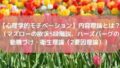こんにちは、HALです。
・過程理論について知りたい
・ブルームの期待理論について知りたい
・ロックの目標設定理論について知りたい
モチベーションについて知りたいけど、たくさんの種類があってわからないという人もいます。
そこでこの記事では、経営学的なモチベーションの過程理論について、特にブルームの期待理論とロックの目標設定理論について解説します。
この記事を読むことで、仕事のモチベーションの過程について理解を深めることができます。
過程理論とは

過程理論とはモチベーション理論を大きく分ける際の1つの考え方です。
人はどのように動くのか、モチベーションはHow(どのように)形成・変化するのかに視点を当てた理論です。
経営学的に、ビジネスの現場で組織のメンバーのモチベーションをどのように高められるか・モチベーションを操作できるかという問がありました。
これに対して、モチベーションのプロセスを明らかにしたのが過程理論です。
外発的動機づけと分類されることもあります。
外発的動機づけとは、他者の評価、報酬や罰など外部の要因によって物事に取り組むことです。
ブルームの期待理論やロックの目標設定理論などが当てはまります。
詳しく見ていきましょう。
ブルームの期待理論

経営学・心理学教授のビクター・ブルームによって提唱されたモチベーション理論の1つです。
対象を合理的な人と仮定して、仕事へのモチベーションが発生する過程を計算式によって明らかにしました。
モチベーション発生の計算式
ブルームは、モチベーション発生の計算式を次のようにしました。
「モチベーション=期待×誘意性×道具性」
期待
期待には次の2つがあります。
「目標を達成することで報酬が得られるという期待」と、「戦略によって目標を達成できるという期待」です。
期待を連鎖させながら良い結果を実現するためには、3つの要素が必要です。
・個人の能力や適性に合った目標の設定
・目標を達成するための戦略の設定
誘意性
誘意性とは、提示された報酬に対して魅力を感じる度合いのことです。
努力すれば魅力的な報酬を得られると思えるほど高くなります。
道具性
目標を達成した結果、更に上の目標を達成するためにどれくらい役立つかの度合いのことです。
努力が魅力的な報酬と自分の成長に繋がることで、モチベーションを高めることができます。
ロックの目標設定理論

アメリカの心理学者エドウィン・ロックによって提唱されたモチベーション理論の1つです。
モチベーションの違いは目標設定の違いによって生じるとしています。
モチベーションが高まる目標設定
次の2つの条件が満たされた場合に、人間は目標達成に向けてモチベーションが高まります。
・目標が具体的かつ明確なこと
目標が明確で困難であることで、注意力や努力の見込み、持続した行動、手順や工夫をすることができます。
無理やりではなく、目標に自分が納得していることが必要です。
フィードバック
目標設定にフィードバックが加わるとよりモチベーションを高められます。
人間は困難な目標を達成したときに、満足感や自信、次の目標達成への意欲を高めます。
フィードバックで目標達成度を確認することが大事です。
フィードバックは回数ではなく、早めに行うことが効果的です。
モチベーションに関する本
心理学的モチベーションについては、以下の記事をご覧ください。

近代的モチベーションについては、以下の記事をご覧ください。
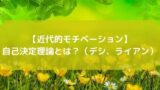
まとめ
・ブルームの期待理論は、対象を合理的な人と仮定して、仕事へのモチベーションが発生する過程を計算式によって明らかにした理論。
・モチベーション発生の計算式は、モチベーション=期待×誘意性×道具性。
・ロックの目標設定理論は、モチベーションの違いは目標設定の違いによって生じるとした理論。
・モチベーションが高まる目標設定は、目標がある程度困難なこと・目標が具体的かつ明確なこと。